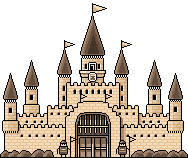<ぶらり奈良>
【古都奈良の文化財】
単一施設での世界遺産登録ではなく
8つの資産全体がひとつの文化遺産として登録されています
奈良に都がおかれたのは710年のことです。
それから1300年近くの時が流れた1998年の12月、
京都で開かれた第22回世界遺産委員会で、
「古都奈良の文化財」の世界遺産リストへの登録が決定しました。
<春日大社>
全国に3000社ある春日神社の総本社である春日大社。
藤原氏の氏神として有名。
創建以来、聖域とされ守られてきた原始林の中に
鮮やかな朱塗りの社殿が鎮座しています。
古くから神の降臨する山として神聖視されていた
春日山・御蓋山の西麓に、四柱の神々をまつったもので、
藤原氏や朝廷の崇敬をうけて繁栄しました。
  
約2000基の石燈籠、約1000基の釣燈籠、
合わせて約3000基の燈籠が立ち並ぶ春日大社。
800年の昔より貴族や武士を始め広く一般庶民より奉納されてきました。
|

二之鳥居 |
境内には約2000基の
石燈籠が並びます
 |

伏鹿手水所 |
神鹿をモチーフにした手水所
神が白鹿に乗って奈良の地にやってきた
とされていることから、
鹿が神使とされています。
 |

南門 |
現在の正門。
正面の楼門で高さは12m、
鮮やかな朱色の荘厳な門 |

中門・御廊 |
御本殿の直前にある楼門
高さは10mと中門から左右に約13m、
鳥が翼を広げたように延びる御廊
 |

社頭の大杉 |
春日大社本殿のそばにそびえ立つ
高さ25mの杉の大木

「槙柏」と呼ばれる木が
斜めに伸びており隣接する直会殿の屋根
を突き破っています |

釣燈籠 |
御手洗川を挟んで境内の釣灯篭
境内には約1000基の
釣燈籠が吊られています
 |